トレンドトピック
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
1/10
スヴェン・ベッケルトの世界の綿花産業の発展の歴史を読み終えたところです。主なテーゼは少し繰り返しで、時には少し苦労することもありますが、貿易と産業政策の歴史に興味がある人にとっては読む価値があります。
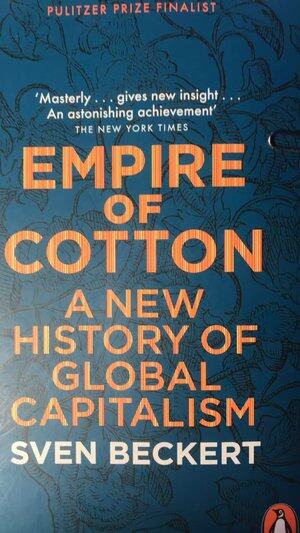
2/10
これらの経済史の興味深い側面の1つは、主流の学術経済学者が理解するのに非常に苦労していることですが、貿易パターンと比較優位が「自然」ではなく、政策や制度から直接現れる程度です。
3/10
ベッケルトは、綿花商人は「自分たちの貿易が地方、国、世界の政治に深く組み込まれていることを早くから理解していた」と書いています。彼らは、国家が市場に介入するのではなく、市場を構成することを本能的に理解していました。」
4/10
彼は、綿花繊維の実際の栽培を除いて(そしてそこでも、あなたが思っているほどではありません)、綿花生産における比較優位について「自然な」ものは何もなかったことを示しています。それとそれに伴う生産性の向上は、政策と制度の創造でした。
5/10
さらに言えば、綿紡績と製織に関連するはるかに速い生産性の伸びの恩恵を受けたいと願う、より強力な国への移行を制限または奨励する政策によって、比較優位が(特にインドから)シフトされる可能性があります。
6/10
経済学者は、かつて経済史をこの主題を理解するための基本として取り憑かれていました。彼らはもはやそうではなく、可能な限りそれを避けているようですが、おそらく主流の経済モデルに疑問があることに気づかずに歴史を読むことはできないからでしょう...
7/10
そして、せいぜい、特に貿易に関しては、あまりにも限定的です。それは、これらのモデルが機能するために単純化された仮定を必要とするからではなく、むしろ、それらを機能させるように設計された仮定でのみ機能し、これらの仮定があまりにも頻繁に間違っているからです。
8/10
貿易は政治的、法的、金融的、構造的な制度に組み込まれており、世界統合と国家主権の間のトレードオフにおいて国によって異なる立場を選択する世界では、これらのモデルの予測的および分析的価値は非常にランダムです。
9/10
たとえば、インドは世界統合を「選択」しましたが(つまり、植民地支配者がそれを選んだ)、イギリス(そして後にフランスとドイツ)は非常に厳しい形態の経済主権を選択しました。綿紡績と製織という大きな賞品がどちらにシフトしたかを推測するのは難しくありません。
10/10
いずれにせよ、強力な国家、大規模なグローバルアクター、弱い労働者の世界で、貿易パターン、貿易の不均衡、比較優位、生産性の向上がどのように決定されるかを見たい人にとって、この本は非常に啓発的です。
60.52K
トップ
ランキング
お気に入り













